難病の弟と過ごした日々 ― きょうだい児としての私の記録
- harmonia77
- 7月4日
- 読了時間: 3分
更新日:7月14日

病名がつくまでの長い時間
弟は、私より3歳年下で、3歳の頃に膠原病のような症状を発症しました。何度も検査を受けましたが、当時の医学では診断が確定できず、最終的に東京の慶応義塾大学病院で「結節性多発動脈炎」と診断されました。以来、治療と痛みとの闘いが続き、ペンタジンという強い鎮痛薬を父が管理して使用していました。
/
小さな頃の家族内での立ち位置
弟が病気だったため、私は小さい頃から「わがままを言ってはいけない」と自然に思うようになっていました。兄は3歳上、姉は5歳上。家の中で何か話し合いがあると、兄・姉・母で話していて、私はその輪には入れませんでした。自分の気持ちを言葉にすることが難しく、特に夏の宿題であった絵日記は苦手でした。言葉を綴ることが重荷に感じられたのです。国語が嫌いになった一方で、書道は好きで塾にも通い、銀賞は取るものの金賞には手が届かず、絵画でも同じような経験をして、「私はいつも“2番手”」という感覚が心に残りました。
/
共に暮らす中で見えた距離と責任
弟は中学生の頃から弱視となり、将来は鍼灸師になる道を選び、盲学校に進学しました。その頃、私は看護師として浜松市の病院に勤務しており、弟と同居することになりました。私は夜勤もあり、生活リズムが安定しない中での同居生活。医療職として、ペンタジンの頻回使用に対して習慣性の問題を感じていた私は、弟に対して厳しい態度をとることもありました。
弟は2度、睡眠薬を大量に服用して自殺未遂を起こしました。母から「弟がご飯を作ってくれないと言っている」と懇願され、夜勤明けで疲れていても、弟のために食事を用意しようと努めました。冷蔵庫にあるもので食べてほしいと思う気持ちと、十分にできていないという後悔の思いが混在していました。
/
術後に見た“弟の最期”
ある日、弟は激しい腹痛で緊急入院しました。開腹手術の結果、消化管の血流が著しく障害されており、ピンク色をしているはずの腸が白く変色していたそうです。担当の医師が私に、切除した腸を見せてくれました。それはまるで、使い古されてボロボロになった雑巾のようで、その印象が今でも鮮明に心に焼きついています。手術後も容体は好転せず、弟は24歳という若さでこの世を去りました。
/
「支えた」という感覚ではなく
人からは「支えていたね」と言われることもあります。でも、私は自分を“支えた側”だとは思っていません。弟が病気だったこと、家族が弟を中心に回っていたこと、それに適応しながら私は生きてきただけでした。私は「きょうだい児」として、自分の思いを整理しきれずに大人になりました。そして今、あの時に言葉にできなかったことを、少しずつ文章にしています。
/
今につながる思い
この体験は、私の看護師としてのキャリアや、今行っているカウンセリング、医療職向け研修、家族支援の土台になっています。当時の私は、誰にも話せない気持ちをたくさん抱えていました。だからこそ、今同じように誰にも言えずに悩んでいる誰かに、少しでも寄り添えたらという思いで、私は活動を続けています。
「あなたにも似た経験があれば、ぜひご感想をお聞かせください。」
私がこうした家族との経験で感じたこと、考えたことは、現在提供している「患者支援」「家族支援」「接遇・コミュニケーション研修」にも活かされています。家族関係や看護・医療の現場でコミュニケーションに悩む方、同じような経験をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
読者の声より(匿名)
「心の中は誰にも見えないですよね。その思いを持ち続けながら大人になります。インナーチャイルドと向き合って自分が癒してあげないと、その時々で前に進むことができないことがありますね。尾高さんの今の活動が、今を苦しんでいる人々に安堵をもたらす場になりますね。」

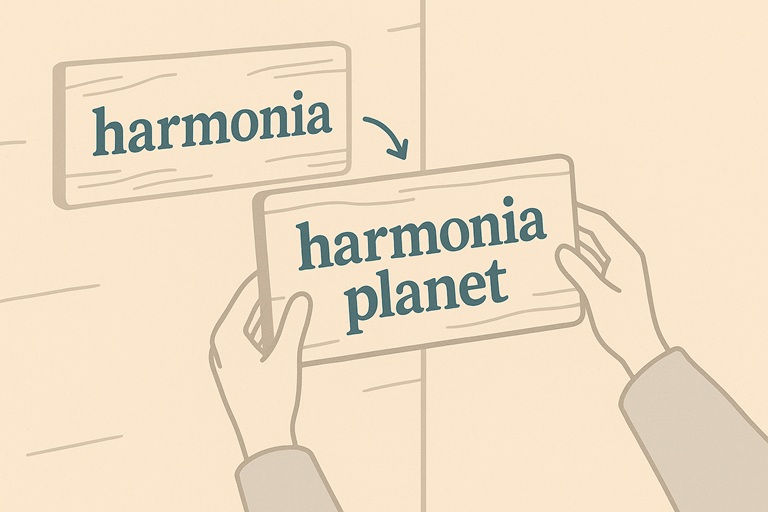


Comments