choosing wisely 第1弾“日米の医療文化から見える「選ぶ力」の大切さ”
- harmonia77
- 8月1日
- 読了時間: 4分

<はじめに──「おまかせ医療」から脱け出すために>
私はこれまで、看護師として長く医療機関で仕事をしながら、50歳を過ぎてからアメリカ留学を経験しました。その中で、日米の医療文化の違いを身をもって感じる出来事がいくつもありました。
日本では、丁寧で手厚い医療が「安心」の象徴とされる一方で、アメリカでは、「本当に必要な医療」を選びとる姿勢が重視されます。そこには、制度の違いも背景にありますが、受け手である「患者」の意識の差も大きいのです。
<アメリカの「患者が選ぶ医療」──短い入院と強い自立>
最近、アメリカ在住の友人から、義理の娘さんが肝移植手術を受けた際の話を聞きました。なんと入院期間はわずか1週間。日本なら1か月から2か月は入院するケースが多いでしょう。逆に日本では、ドナー側の入院が1週間程度とも聞きます。
また、私の留学中に80代の知人女性が足を骨折したときも、入院は1泊だけ。彼女の自宅は坂道の途中にあり、玄関先は石段、家の中も段差が多い構造です。心配で何度か見に行きましたが、退院直後から彼女は自力で移動し、日常生活を再開していました。
「これは日本では考えられない…」と思わずにはいられませんでした。
<私自身の体験──レントゲンなしの診断に驚く>
滞在中、私自身もスキー場で転倒し、足を痛めて受診したことがあります。医師はしっかり患部を診てくれましたが、レントゲン撮影は「必要なし」と判断。撮影されませんでした。日本なら、ほぼ間違いなくレントゲンを撮るでしょう。最初は「これで大丈夫?」と戸惑いましたが、診断と説明に納得し、安心して帰宅しました。
また、甲状腺機能低下症のため現地で受診予約をしていたある日、大雪で30分遅れて到着したところ、「予約外なので診察できない」とあっさり断られ、別の医院を紹介されるという経験もありました。日本では、こうした事情があれば柔軟に対応してもらえることが多いので、その厳格さに驚いたものです。
<日本の医療の「丁寧さ」と「おまかせ」の文化>
帰国後、高血圧の治療中に、薬を飲んでも改善しないことから「何か病気が隠れているのでは」と自ら担当医に大学病院への紹介をお願いしました。結果は「原発性アルドステロン症」。私が医療職だったから気づけたのかもしれません。もし一般の方であれば、「年齢のせい」と見過ごされていた可能性もあったでしょう。
日本の医療は「丁寧で安心感がある」ことが美徳とされていますが、その一方で、患者が医療に「おまかせ」しすぎている場面も多く見られます。
<アメリカの現実──任せきれないからこそ、知る努力を>
アメリカでは、自己責任の考えが基本にあり、医療保険の種類によっても受けられる治療は異なります。薬ひとつにしても、患者自身が薬効や副作用を確認し、理解したうえで服用するのが当然です。
私も、「それは本当に必要な治療か?」「他の選択肢はあるか?」と常に自分で調べ、質問しながら診療に臨みました。「自分の体は、自分が知る」──その姿勢が求められているのです。
<Choosing Wisely──「賢く選ぶ医療」とは>
こうした経験の中で出会ったのが、「Choosing Wisely(チュージング・ワイズリー)」という考え方です。これは、「本当に必要な医療を見極め、過剰な検査や治療を避けよう」という国際的な医療の潮流です。
医療費削減のためだけでなく、患者の安全性・QOL(生活の質)向上のためにも、慎重で賢い選択が求められています。そしてそれは、医療者だけでなく、患者一人ひとりの姿勢にもかかっています。
<終わりに──「必要な医療を、必要な人に」>
「医療は、使えば使うほど良い」という時代は終わりを迎えつつあります。必要な医療を、必要なときに、必要なだけ──それが、限られた資源の中で医療を持続可能にする鍵です。
この「Choosing Wisely」の考え方は、私が提供している「患者支援」や「職員研修」では、このように“自ら考え、選び取る力”を育む視点を大切にしています。次回のブログでは、「医師の専門性」や「診療の質」についてさらに掘り下げていきたいと思います。
✅ さらに詳しく学びたい方は、Choosing Wisely Japanの公式サイトをご参照ください。👉 https://choosingwisely.jp/ ※リンク先は一般公開されており、医療者・市民の誰もが学べる内容が掲載されています。

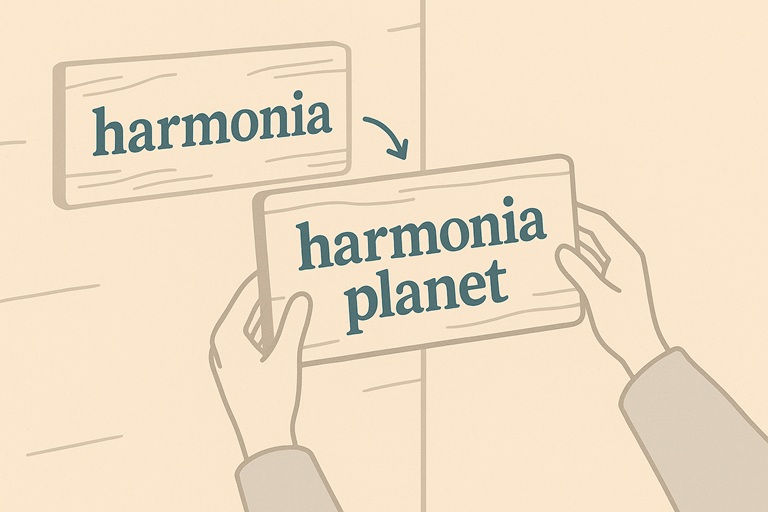


今回は特に興味深く読ませてもらいました。私は看護師で、病棟勤務を経て、現在は施設や居宅の訪問看護をしていると、その頃には気付かなかった日本の医療文化に対して疑問に思うところが多々出てきました。端的にどちらが良い悪いということは言えませんが、これからの医療のあり方を社会全体でもっと考えていかなければなぁと感じました。(LINEでコメントを貰いましたので、了解をいただいた上で載せて貰いました。)
「本当に必要な医療」についてですが、
90過ぎた男性が公共交通機関を使ってM病院からT大学病院へ放射線治療のために毎日通って、そのうち疲労だったのか、訪問看護師が定期訪問をしたらリビングで倒れてました。この超高齢男性が、公共交通機関を使って毎日通っている姿を大学病院の医師や看護師は想像してましたでしょうか?患者側の責任も然り、医療を提供する側の想像力が微塵も無く、治療が大前提の日本の医療がいかにQOLがお粗末か‼️(LINEでコメントを頂き、了解をいただいて投稿させてもらいました)