第一部:50歳を前に、私がアメリカ留学(2000年~2002年)を決めた理由
- harmonia77
- 7月11日
- 読了時間: 3分

<出向先での厳しい環境と退職の経緯>
1999年、私は大学病院から都内の病院への出向を命じられました。「教育婦長」としての出向でしたが、実際の目的ははっきりしないまま、片道2時間半、4本の電車を乗り継ぐ通勤が始まりました。朝は5時10分頃の始発に乗り、帰宅は21時頃という日々。体力的にも精神的にも厳しい状況でした。そんなある日、病院の理事長から呼ばれ面会しました。理事長は湯呑みのお茶を指差し、「私がこの色を赤と言ったら、例え医者であっても赤という」と言ったのです。私はその意味を完全には理解できませんでしたが、「曲がったことでも従え」ということだと感じ、大きな落胆を覚えました。すぐに本院の大学病院の事務長と看護部長に相談しましたが、状況は改善せず、結局その年度末で退職を決めました。ちょうどその年の1月8日、40代で脳卒中を患い車椅子生活となった姉の夫を、長年介護してきた姉が52歳で急死したばかりでもあり、私の心にはいろいろな思いが渦巻いていました。
<過去の短期研修とDPC制度への危惧>
1993年、私は大学病院からの派遣で、2週間ほどアメリカで研修を受けたことがありました。当時は英語が苦手で、現地の人々とのコミュニケーションに苦労しました。それでもこの研修で、DRG/PPSというアメリカの医療費支払い制度について学ぶことができました。DRGは入院患者を臨床的に似たグループに分類し、PPSはそのグループごとに一定額を支払う方式です。その後、日本でも「DPC(診断群分類包括評価)」として、これに近い方式が導入されるという情報を耳にしました。私はこの制度がもたらす影響を危惧し、研修先の指導者に質問しました。「この仕組みだと、合併症のある患者が受け入れられなくなったり、治療できる病院が限定されたりするのでは?」と。指導者の答えは「そういった傾向があります」というものでした。その後、日本では2003年にDPCが特定機能病院を中心に導入され、今では対象病院が広がっています。
<挑戦:自力で留学手続きを進めた>
私は医療制度の変化をより深く理解したいと思いました。そして何より、あの苦しい時期に「気分転換したい」という気持ちもあり、再びアメリカで学ぶことを決意しました。当時、私は50歳を目前にしており、更年期の症状にも悩まされていました。日本の知人を通じて、シアトル在住で日本語が堪能なアメリカ人女性を紹介してもらい、その方を頼りに渡米することにしました。私の留学は、中学・高校生や大学生のそれとは違い、自分ですべて手配する必要がありました。なんとかワシントン大学(UW)の看護学科の教授とコンタクトを取り、思いを伝えましたが、「まずは英語力を身につけてから」との返答。そこで、UW進学前に多くの留学生が通う Bellevue Community College(現Bellevue College) の International Programs に入学することにしました。留学に必要な手続きはすべて自分で調べ、アメリカ大使館にも何度も足を運びました。留学前には2度シアトルを訪問し、ホームステイ先も決めました。そして、その年の5月、いよいよ渡米したのです。
「この挑戦が、今の私の活動の礎にもなっています。これから少しずつ、そこでの出会いや体験から得た気づきを綴っていきます。」

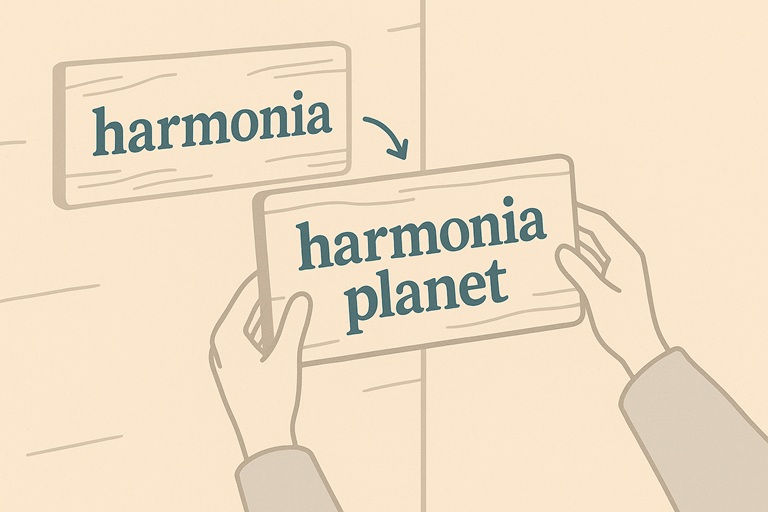


Comments