家族で見送った父、一人にさせた母──看取りの経験から学んだこと
- harmonia77
- 6月21日
- 読了時間: 4分
更新日:7月14日
<はじめに>
大切な人の最期に、どう向き合うか。これは、長く看護の仕事に携わってきた私にとっても、決して簡単な問いではありません。
父と母、それぞれの最期の時間を共にした中で感じたこと、このふたりの看取りは、私身の人生を大きく変える経験になりました。
今日はその記憶を、記してみようと思います。
<父の最期:手術の決断と、家で迎えた穏やかな別れ>
私の父は1998年7月、80歳になったばかりで亡くなりました。胃がんが見つかった時にはすでに肝臓と膵頭部に転移しており、余命は1年もないと診断されました。糖尿病と狭心症という持病もあり、手術には大きなリスクが伴っていました。
私は看護師として、そしてその病院に以前勤務していた立場から、主治医と相談のうえ、父への告知と手術の意思確認を私が行うことにしました。事前に母と兄姉にも説明し、了承を得た上で、病院の一室で父とふたりきりになりました。
静まり返った空間の中、「胃がんだった」と伝えました。そして、手術の必要性や、放置すれば胃の通過が妨げられ食事ができなくなること、手術には糖尿病による創傷治癒の遅れといったリスクがあることも率直に伝えました。「どちらを選んでも良い。お父さん自身で決めてほしい」と。
転移については、主治医と相談のうえ父には伝えませんでした。父は「手術を受けたい」と希望し、バイパス術を受けました。術後は比較的順調で、退院後は自宅で、民謡の仲間や戦友を招いて民謡大会を開いたり、家族で伊豆へ80歳の祝い旅行に行ったりと、充実した時間を過ごすことができました。
しかし、半年も経たないうちに衰弱が進み再入院。食事ができなくなり中心静脈栄養が必要となりました。1週間も経たないうちに「家に帰りたい」と父が言いました。私たちは再び家族で話し合い、自宅での看取りを決意しました。
搬送車の中で父がぽつりと「俺は死ぬのか?」とつぶやきました。私は何も言えず、ただ涙を流すだけで、その私の姿をみて父は悟ったようでした。帰宅前には、家族とともにアルフォンス・デーケン先生の「死の準備教育」を用いて勉強会を行い、父を迎える心の準備をしました。
当時は訪問看護がまだ一般的ではなかったため、父の知人である開業医に訪問診療を依頼し、私は中心静脈栄養の管理と夜間のケアを担いました。日中は家族で分担し、父を支えました。自宅に戻って4日目の朝、仮眠中だった私を兄が「おやじ、息をしていないみたいだ」と呼びに来ました。私は父の死を確認し、主治医の到着までに死後の処置を自ら行いました。
父の看取りは、家族全員が協力し合った結果、穏やかで心残りの少ない別れとなりました。
<母の最期:一人で背負った介護と心残りの看取り>
一方、母の死は2010年7月。80歳まで経理の仕事をしていた母は、退職後に認知症が進行しました。兄嫁との関係も難しくなり、私はデイサービスの導入を勧めましたが、母は強く拒否。なんとか本人が体調不良を訴えたタイミングで病院に連れて行き、デイサービスも数回私が同行して馴染んでもらいました。
私は神奈川県に住んでいたため、週末には母を迎えに行き、自宅に泊めたりドライブに連れ出したりして過ごしました。米寿の祝いもしましたが、その1年後、肺炎で入院。兄から「もう家では見られない」と相談され、私の勤務先の療養病床に転院させました。
入院から1か月も経たないある日、友人の選挙応援に出かけた帰路、病院から「呼吸停止」との連絡が入りました。急いで駆けつけましたが、すでに母は亡くなっており、蘇生もできませんでした。母は誰も見舞いに来ないことを寂しがっていたのに、最後の瞬間に寄り添えなかった悔いが今も残っています。
<二つの別れから学んだこと→家族の支えと、外部の手の必要性>
父のときは、家族が一丸となって支え合い、共に見送ることができました。母のときは、家族関係の距離があり、私一人が背負う形になってしまいました。看取りや介護は、家族の絆と「共に思う力」が何よりも大切です。それが難しいときこそ、専門家や外部支援との連携が必要なのだと強く感じています。
父と母、ふたりの看取りを通して私の学んだことは、「支える人」には支えが必要だということです。
看護や介護の現場で、「誰かのために頑張っている方」に、少しでも安心と力を届けられたらと思っています。
心と体のバランスが崩れそうなとき、誰にも相談できないと感じた時、どうぞ一人で抱えず、お声掛けください。
この看取りの経験は、私が現在提供している「家族支援」「接遇・コミュニケーション研修」「患者支援サービス」の基盤にもなっています。介護や看取りの現場でお悩みの方、現場で役立つコミュニケーションを学びたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
☞詳しいプロフィールやサポート内容はこちらからhttps://www.harmonia2.info/

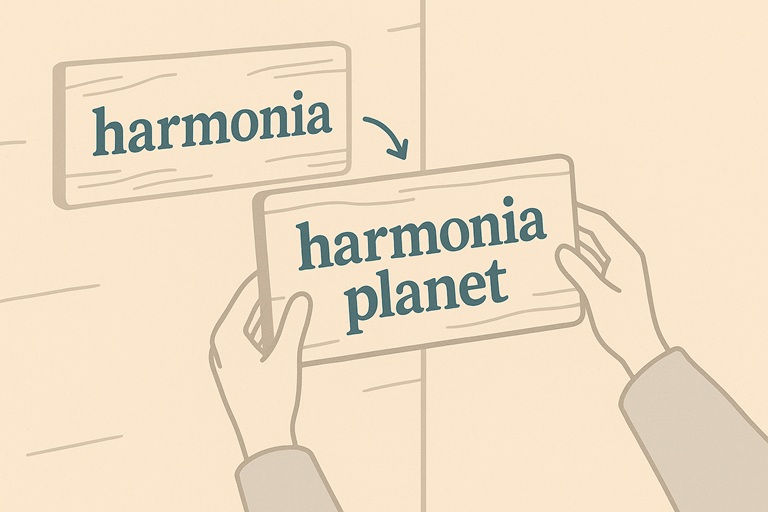


Comments